コース案内
学部卒学生向けには,2つのコースがあります。
(入学案内・小学校教員免許取得コース案内)
授業力開発コース
目標,目指す教師像
教職に関する学修をさらに深めるとともに,2年間の実習を通して授業の実践力を高め,大学院修了後に即戦力として勤務できる教員を目指します。
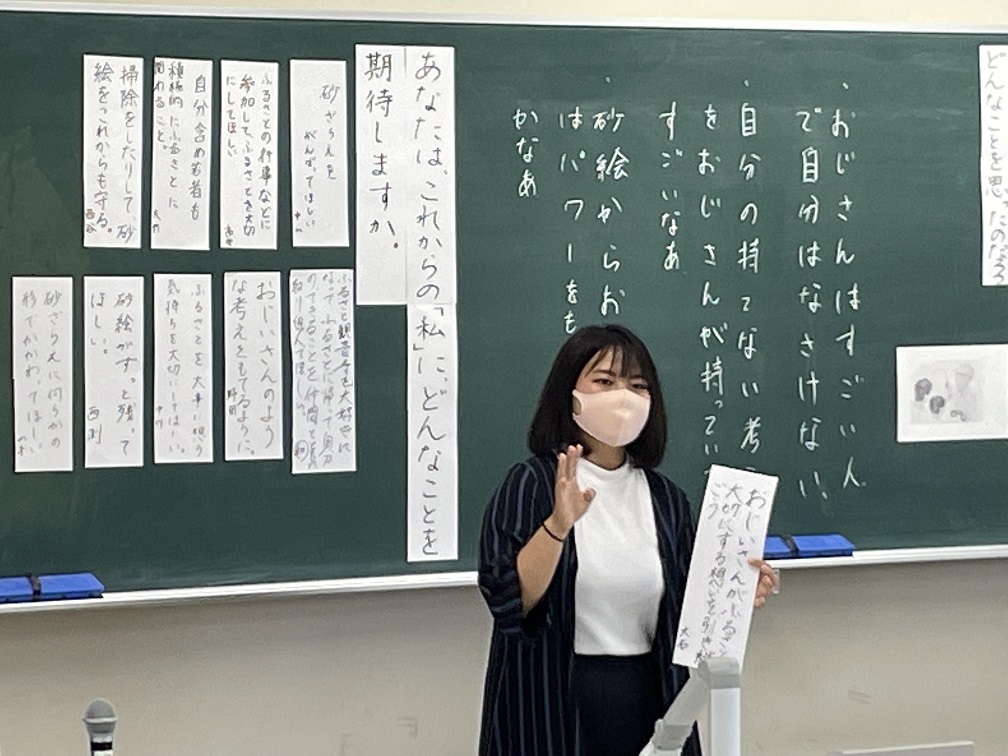
実習について
2年間,週に1度のペースで附属学校(1年次)や大学近隣の連携校(2年次)へ実習に行きます。大学院で学んだことを実際の学校教育と関連づけて学修を深めるだけでなく,授業実践を通して授業力を高めます。
附属学校での実習(1年次:学校臨床基礎実習Ⅰ)
高松,坂出のいずれかの附属学校に通い,附属学校の子どもたちと触れ合いながら,大学院で学んだことを実際の学校教育に関連づけ,また,子どもたちが1年間でどのように成長するのか,具体的に学びます。また,経験豊富な附属学校の教員の授業から指導技術を学ぶとともに,授業実践では附属学校の教員から直接指導を受け,授業力を高めることができます。

連携校での実習(2年次:授業力開発実習)
大学近隣の連携校や県内各地の連携校に通い,1年次の附属学校での実習についての学修を深めます。また,学校現場での教師の仕事について具体的に学び,大学院修了後に即戦力として勤務できるよう,教師としての力量を身につけます。
附属学校での実習(2年次:探究実習)
9月に2週間,附属学校で再度実習を行います。1年次の附属学校での実習について学び直すだけでなく,学部実習生のサポート役を務めながら,教師として互いに学び合う成長過程を実際に経験することができます。
時間割例
(1年前期)
特別支援力開発コース
目標,目指す教師像
特別支援教室「すばる」や附属特別支援学校等における指導事例の検討や実習,発達障害に関わる医療・療育機関等における実習など,演習と実習に重点を置いたカリキュラムを構築し,通常の学級に在籍する発達障害等のある児童生徒,特別支援学級,特別支援学校に在籍する児童生徒への指導支援を行い,特別支援教育に関わる校内体制を確立する要となる教員の養成を目指します。
実習について
学校臨床基礎実習(1年次)
特別な教育的ニーズのある子どもに対する実践的指導力の向上を図ります。附属特別支援学校の実習の場として,知的障害児に対する生徒指導や授業の様子を参観して,支援環境の改善,支援の手立ての工夫,附属特別支援学校教員の指導や援助の方法,校内連携や家庭等との連携による支援体制の構築について学びます。学部段階における実習を踏まえ,小学部,中学部,高等部のいずれかにおいて実習を行います。前期を通して子どもの変容を体験的に理解できるようにします。また,附属特別支援学校教員の助言や指導のもと,教材・教具の作成,授業及び支援に参画をします。
特別支援教育指導実習(2年次)
特別支援教室「すばる」を実習の場として,特別な教育的ニーズのある児童生徒に対するアセスメントと個別指導に関する指導実習を行います。来談者への教育相談,コンサルテーション,スーパーバイジング及び個別指導を体験したうえで,発達障害等による特別な教育的ニーズのある児童生徒への個別指導を担当し,対象児の課題に関する分析・評価,個別の指導計画の作成,実際の指導方法・技術について実習します。個別の指導計画の作成を通して,児童生徒の特性に応じた短期目標,長期目標を設定することができることを目標とします。
探究実習(2年次)
附属特別支援学校で知的障害児に対する生徒指導,授業の様子を参観して,支援環境の改善,支援の手立ての工夫,指導者の指導や援助の方法について学びます。また,通級指導教室を見学参観して,指導形態・時間,自立活動を中心とする具体的な指導内容,学級担任等に対する相談・助言等の通級による指導の実際を知るようにします。さらに,発達障害外来のある医療機関,相談支援にあたる支援センター等での診察や相談の様子を知り,教育機関とは異なる立場の様子を知り,協同連携の在り方,ネットワークの築き方等の実践力の向上を図ります。
時間割例
(1年前期)
修了生の声
大切にしたいこと
教職大学院を修了し、小学校に勤務して3年になります。現在、理科の部会に在籍しており、今年度、市内で研究授業をさせて頂きました。改善すべき点は多々あったことと思いますが、実験結果に対し、子どもが生き生きと意見を交わし合い、日々の生活と繋げて考える姿を見ることができました。大学院在籍時に研究をしてきた教科とは異なりますが、子どもの主体性や意識の流れなど、大切にしたいと留意した部分は同じであると考えています。日々の授業においても、子どもが真剣に課題に向き合い、主体的に学ぶことができるよう、今後とも精進して参りたいと思います。
(平成30年度授業力開発コース修了生)
大学院生から教員へ
教師になって約一年、大学院での学びを思い出すことがたくさんありました。基本的な指導案の書き方、授業準備、子どもたちとの関わり等、授業や実習で学んだことを自分のペースで実践しています。また、分からないことがあれば、大学院の先生方や共に学んだ先生方に相談にのっていただくこともありました。
成功も失敗も、成長するための大切な経験です。子どもたちと前を向いて進むために、大学院生時代から経験してきたことを大切に、「学び続ける教師」であろうと思います。
(令和2年度授業力開発コース修了生)