2.教育学部における国際交流(2) 江西師範大学
3.教育学部における国際交流(3) コロラド州立大学
4.教育学部における国際交流(4) 韓国交流
5.教育学部における国際交流(5) 新しい国際交流
6.教育学部における国際交流(6) チェンマイ大学
1.教育学部における国際交流(1) クライストチャーチ総合技術大学
2.教育学部における国際交流(2) 江西師範大学
3.教育学部における国際交流(3) コロラド州立大学
4.教育学部における国際交流(4) 韓国交流
5.教育学部における国際交流(5) 新しい国際交流
6.教育学部における国際交流(6) チェンマイ大学
![]()
教育学部における国際交流(3):コロラド州立大学
香川大学では,教育目標を、「豊かな人間性と高い倫理性の上に,幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備え,国際的に活動できる人材を育成」と掲げ、「諸外国との学術・文化交流を推進し,国際交流の拠点」となるべく活発な国際交流活動を展開してきました。(香川大学憲章、2007年3月26日制定)
教育学部が主管学部となり、香川大学とアメリカ合衆国コロラド州立大学(Colorado State University, CSU)は、2002年10月8日に研究者交流を中心とする学術交流協定を結びました。以来、毎年同大学の研究者を招聘し、附属学校園との交流活動や共同研究を推進し、交流を深めています。
大学の紹介及び交流の特徴
1870設立。1935年に州立となり、1957年に現在のコロラド州立大学に改名されました。コロラド州立大学は、現在、約3万余人の学生・教職員がこのキャンパスに集っており、80%の学生が州内の学生です。キャンパスは街の中心に位置し、830エーカーの広大な敷地に100棟以上もの近代的な建物が立ち並び、世界各国から集まった留学生を含め、国際化にもたいへん積極的な大学で、国際交流を目的としたイベントも学内外でしばしば催されています。
コロラド州立大学はアメリカ合衆国の主要な研究大学の一つです。これまでに4万3千人の学生が修士、博士、獣医の資格を獲得しました。香川大学とコロラド州立大学は研究交流を中心とした学術協定を結んでいます。毎年、様々な学部の研究者が行き来し、講演、講義等を行うと共に、共同研究を展開しています。



キャンパスから農場、遠くの山々を臨む(左 3月上旬 中 10月上旬) 町にもキャンパスにも野生動物がいっぱい
2004年から2007年現在までの交流実績
渡米 2004年 1名 2005年 3名 計4名
来学 Ms. Barry Carroll(2004.10.4-10.9)
Prof. Stephan Thompson (2005.3.11-3.19)
Prof. Masako Beecken(2005.6.7-6.12)
Prof. George Collins(2005.11.19-11.22)
Prof. Masako Beecken(2006.6.3-7.13)
Prof. Anthony T. Tu(2006.10.5-10.14)
Prof. Masako Beecken(2007.5.26-5.28)
他 8名の日本語専攻学生
Prof. Stephan Thompson (2007.8.22-9.3)
計16名
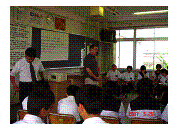

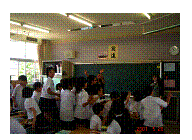 ←大学・附属学園での活動
←大学・附属学園での活動
訪問した教員の声:
CSUではここ5?6年日本語を勉強する学生が年々多くなっています。2006年度は、日本語履修学生登録数は中国語を抜き、スペイン語に次いで2番目に多くなったそうです。日本語コースでは日本からのシニアのボランティアの方もたくさんCSUで働いています。コロラド州は物価もほどほどで、いまでも割合白人比率が高くアメリカらしさを満喫するにはもっとも適した州の一つといえるでしょう。各国からの留学生は、まずIEP(Intensive English Program)で徹底した語学教育を受け、学部の講義を履修するようになります。自然がいっぱいのCSUへ一度訪問してみてください。


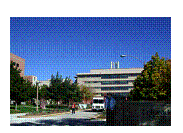
授業の合間に移動する学生(左は図書館) 学生会館 南門からYatesHallを望む 教育学部 高木由美子
ホームステイ受け入れ学生の声:
今回ほど、スリルとサスペンス(はなかったが)に富んだ受け入れは、これから先もないであろう。百日咳のため大学が休校になり、「行事はどうなるのであろう?」と心配したのは、受け入れ前夜であったからである。夜中まで、受け入れ態勢についての調整、確認、連絡に奔走された高木先生に改めて「本当に、お疲れ様でした!そして、ありがとうございました。」JR高松駅にて、彼らを出迎えた。一向8人の中には、日本語を勉強し始めて1年目の学生と2年目の学生がいた。彼らを車に乗せて、牟礼町にある、イサム・ノグチ庭園美術館へ向かった。空間全体がイサム・ノグチの作品とされている庭園美術館に足を踏み入れたとき、また、イサム・ノグチの代表作である「エナジー・ヴォイド(1971年)」(ヴォイド=空っぽ)の前で腰を下ろしたとき不思議な感覚におそわれた。彼らこそこの場所にマッチしている。ロサンゼルスで生まれ、ニューヨークで勉強したイサム・ノグチの作品を日本人の私たちより、より、相通ずる感性で楽しんでいるように思われた。
かれら留学生の中には、将来日本で就職を希望している学生、日本で教師になりたいと希望している学生がいた。日本をより理解し、これからの人生に役立てようと、遠くアメリカ中央部砂漠の地コロラドから訪れた学生諸君に心よりエールを送りたい! 
中西公子
今回のコロラド大学の学生と共に過ごした2日間はとても自分にとってよい経験となりました。過ごした2日間はとても楽しくあっという間に過ぎてしまいました。彼らはとても気さくで優しく、そして何より勉強熱心でした。日本語をとても勉強してきていて、かなりの会話が日本語でできました。それにくらべて私はあまり英語が喋れずにもどかしかったですが、理解しようとしてくれた姿勢がとても嬉しかったです。この出会いを期に、私の中で英語を喋りたい・外国に行ってみたいという気持ちがとても強くなりました。深夜の英会話番組を見て勉強することが多くなりました。英語がペラペラになり、機会があれば是非コロラドに行ってみたいです。今回のような試みがあればまた参加したいです。ありがとうございました。
光吉直哉
コロラド州立大学があるフォートコリンズ市(fort Collins)は、人口約134.000人の中規模都市です。コロラドの州都デンバーから北に約100km、雄大なロッキー山脈の麓にあります。
標高およそ1600m、平均300日間晴天で、年間降水量は360ミリ程度です。Cache La Poudre川が町の中心部を流れ、四季があり、自然に親しむにも最高のロケーション、典型的な大学町で、街の治安もよく、人々もあたたかく親切です。2006年8月号のMoney Magazineによると、「全米でもっとも住みやすい所:Best Place to Live」に格付けされています。皆さんも一度訪れてみてください。
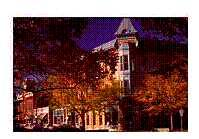


Old town Hoot hillにあるThe Aggieのlandmark ロッキー山脈国立公園
コロラド州立大学http://welcome.colostate.edu/ フォートコリンズ市http://www.ci.fort-collins.co.us/