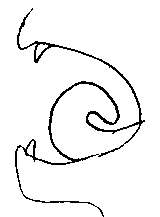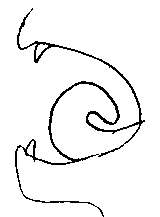
English Phonetics II 2016
「英語の/r/の発音のしかた」というテーマで
右のような図を描いてくれた学生がいました.
別の学生は「図う見ても,テープ聞いても,
結局どおしたらええんかが,わからんやん」と感想を述べてくれました.
どうすればよいか,調べていきましょう.
MEMO
(last modified: 05/13/2019 07:39:55)
- ヘッドホン(イヤホン)とマイクロホンを用意すること。100円ショップの4極プラグのイヤホンマイクもマイク代わりに(なんとか)使えます。
- 発音記号(mirror of Wells, 2016)が文字化けないように,テキストファイル提出時には文字コードを「その他」「unicode/UTF-8」とすること。その他ヘルプのページも参照してください。
- シラバス[ ]内の学籍番号順に教科書の内容について発表。前日正午までにハンドアウト(学籍番号.pdf)をメール添付で提出
- 各自で決定したテーマについて,1月27日にエッセイを提出します。
- 1月27日には各自のテーマについて2~3分発表。その際スクリーンに映すものをA4横で作成し,学籍番号.pdfを当日ネットワーク上のフォルダへ提出。
- テーマは教科書pp.340-347のglossaryの中から選ぶことが望ましい
- A4で8ページ以内,全ページに学籍番号,ページ/総ページを記入。左上にクリップ(ステープラ不可)。手書き不可。
- Plagiarismに細心の注意を払うこと。引用については
「日本心理学会の執筆・投稿の手びき」の31ページ以降の書式を標準とする。
「...と言われている」「...とされている」等の表現は原則不可と心得ること。
- 前期に学習したBBC Sounds of English のページもときどき復習すること。
Course schedule [reg.#]
Term 2
Week 1 (7 Oct) Introduction to term 2 [ID#]
Week 2 (14 Oct) Word Stress 1 (pp. 137-144)[103/106]
Week 3 (21 Oct) Word Stress 2 (pp. 144-149)[107/115]
Week 4 (*26 Oct) Connected Speech 1 (pp. 153-160) [126]
Week 5 (4 Nov) Connected Speech 2 (pp. 160-165) [141/152]
Week 6 (11 Nov) Connected Speech 3 (pp. 166-171) [153/170]
Week 7 (18 Nov) Intonation 1 (pp.179-185) [179/188]
Week 8 (25 Nov) Intonation 2 (pp. 186-192) [202/207]
Week 9 (2 Dec) Intonation 3 (pp. 192-200) [305/310]
Week 10 (9 Dec) Phonology Review 2 [330/341]
Week 11 (16 Dec) In the Classroom [344/512]
Week 12 (*20 Dec) Some questions (pp. 237-248) [520/521/530]
Week 13 (20 Jan) Problem areas [538(-p. 269), 541(pp. 281-283)]
Week 14 (27 Jan) Essay due / Presentation
Week 15 (3 Feb) Defense / Follow-up
Week 1 : Introduction to term 2
<今日の目標>
- 後期シラバスの確認,イントロダクション
- 強勢(stress),高さ(pitch),アクセント(accent)と概念を理解する
- ネットワークを使って音声ファイルの取得と提出ができる
- 標準の環境で音声ファイルの再生とマイクロホンを使った録音ができる
- 発音記号を含む文書を作成し,文字化けしないテキストファイルを提出できる
<今日の課題>
- 三省堂辞書サイトの国語辞典で「橋」「箸」「端」を調べ,数字が書いてある語があることを確認せよ。この数字は何か?
- NHKの新しいアクセント辞典は音の上がり目を示さない。なぜか?
明解国語事典の解説が参考になる。
- ファイルのダウンロードと提出方法に従い,Materialフォルダからmp3ファイルを自分のPCにコピーせよ。
- mp3ファイルをヘッドホンで聞き,ワードで英文を書き取りなさい。
- 音が出ない,録音できないときはオーディオファイルの再生と録音を参考に。
- 英文の下の行に,書き取った英文を
音素表記の発音記号で書きなさい(ɜː=əː, ɒ=ɔなどに注意)。「名前をつけて保存」でテキストファイル「学籍番号.txt」を作りなさい。その際,文字コードを「その他」「unicode/UTF-8」とすること。
- 「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「サウンドレコーダ」を起動し,書き取った英文を,自分の声で録音せよ。ファイル名は学籍番号.wmaとすること。
- テキストファイルと録音したwmaファイルをReportフォルダへ提出せよ。
<今日の目標>
<今日の課題>
- 共有の material フォルダから praat.exe をコピーし起動せよ。
- praat quick tutorial 1を参考に,二つ目の ba に強勢を置いて "ba BA ba ba" と録音せよ。
- エディタ画面をPrtScrキーでワードに貼り付けよ。
- 二つ目の ba と三つ目の ba の周波数(frequency),時間長(duration),強度(amplitude/intensity)を測定し,グラフの下にメモせよ。
- 二つ目の ba と三つ目の ba のフォルマント(縞模様)を見比べて,気づいたことを記入せよ。
- "学籍番号.pdf"をReportフォルダへ提出。
先週の解答例

<今日の目標>
<今日の課題>
- 共有の material フォルダから praat.exe をコピーし起動せよ。
- praat quick tutorial 1を参考に,
"thirteen - thirteen men" と "greenˈhouse - ˈgreen house"の強勢を自分の声でグラフにしなさい。
- "学籍番号.pdf" をReportフォルダへ提出。
Week 4 : Connected Speech 1
先週の解答例

<今日の目標>
<今日の課題>
- 共有の material フォルダから praat.exe をコピーし起動せよ。
- praat quick tutorial 1を参考に,
"Kids like sweets." と "The kids like the sweets." を録音し,(1) 音節数, (2) 文全体の時間,
(3) kids の/ɪ/の始まりから/wiː/の始まりまでの時間,
(3) 強さのグラフの二つの山の間の時間,を測定せよ。
- グラフの下に測定値を表にして書き込み,"学籍番号.pdf" をReportフォルダへ提出。
Week 5 : Connected Speech 2
先週の解答例

<今日の目標>
<今日の課題>
- 共有の material フォルダから praat.exe をコピーし起動せよ。
- "that person" "good boy" "in public"と録音し,学籍番号.wavを保存せよ
- "that person" "good boy" "in public"を発音記号で書き,どのような同化が生じているか説明した学籍番号.txtを保存せよ。
「名前をつけて保存」「書式なし(txt)」文字コードを「その他」の「unicode/UTF-8」とすること。
- 二つのファイルをReportフォルダへ提出。
Week 6 : Connected Speech 3
<先週の解答例>
1. that person
発音記号 /ðæp pɜːsən//
personの語頭の/p/(無声両唇破裂音)の影響でthatの語尾の/t/(無声歯茎破裂音)が/p/(無声両唇破裂音)へ変化する。
2. good boy
発音記号 /gʊb bɔɪ/
boyの語頭の/b/(有性両唇破裂音)の影響でgoodの語尾の/d/(有声歯茎破裂音)が/b/(有性両唇破裂音)へ変化する。
3. in public
発音記号 /ɪm pʌblɪk/
publicの語頭の/p/(無声両唇破裂音)の影響でinの語尾の/n/(無声歯茎鼻音)が/m/(無声両唇鼻音)へ変化する。
<今日の目標>
<今日の課題>
- ハンドアウトの答を学籍番号.txtに記載せよ。
- 教科書171ページ,Activity 15の6つの英文を録音し,
学籍番号.wavを作成せよ。
- 両方のファイルをReportフォルダへ提出。
<今日の目標>
<今日の課題>
- ハンドアウトの答を学籍番号.txtに書きReportフォルダへ提出せよ。
<今日の目標>
<今日の課題>
- material フォルダから rtpitch.exe をデスクトップにコピーし,ハンドアウトを練習せよ。
- 次に // Is that you, Jane? // と // Jane, // is that you? //の2文のピッチのグラフをワード文書に貼り付け,その下に英文と toneの矢印を加えよ。"Jane, is that you?"ではtone unit/thought groupが二つになり,矢印が二つ付くことに注意せよ。praatで録音してグラフを作っても,rtpitchのグラフを止めて貼り付けても良い。後者の場合「ペイント」で色を反転させ白い背景に変えておくこと。
- 学籍番号.pdfをReportフォルダへ提出。
<先週の解答例>

下段のピッチ曲線が二つの tone units/thought groupsになっていることに注目
// ↗jane // is that ↗you //
<今日の目標>
<今日の課題>
<notes for unit 12>
- Activity 1
- まず発音を調べよ
- Activity 2
- 省略や変化のない引用形と並べて比較せよ
- Activity 3
- 省略や変化のない引用形と比較せよ
- Activity 4
- 簡略表記の発音記号は書けるようになること。δ(delta)はð(eth)に書き換えること。
- Activity 5
- 省略や変化のない引用形と比較し,なぜ問題文のような発音になるのか考えよ
- Activity 6
- 省略や変化のない引用形と比較し,なぜ解答のような発音になるのか考えよ
- Activity 7
- 省略や変化のない引用形と比較し,なぜ解答のような発音になるのか考えよ
<先週の解答例>
「お茶飲む」が疑問文に聞こえ始めるには、緑の点を
206.4Hz→322Hzに上げる。
「お茶飲む?」が疑問文に聞こえなくなるのは、緑の点を
402Hz→167.3Hzに下げる。
疑問文に聞こえ始める高さと、疑問文に聞こえなくなる高さが違う理由は、
「お茶飲む」と「お茶のむ?」のそれぞれの最初の音のHzが、前者では280Hz、後者では243Hzである。疑問文の時には低いピッチの音から始まり、それよりも高いピッチの音で終わる。一方疑問文ではない時には、高いピッチの音から始まり、それよりも低いピッチで終わるからである。
<今日の目標>
<今日の課題>
- エッセイのタイトルと予想される結論を
学籍番号.txtとしてreportフォルダへ提出。
- Bainbridge State Collegeの
ビデオを見て,(i) cheating, (ii) plagiarising without intending to, (iii) common knowlege とはどのような場合か説明せよ。エッセイタイトルと一つのテキストファイルにし,学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。
<notes for unit 13>
pp. 211-213 の (b) Explaining the components parts ... と (c) Outlining ... を正確に訳す。
語学の教室で,学習者の気づき(noticing),s/thやl/rの区別(discriminating),
教師の発音の模倣(imitating)と再生(reproducing),
引用形でない自然な発話(contexualizing),
未知語でも発音できる(generating)こと,
間違いが訂正できる(correcting) ことは,それぞれどれくらい大切だと思うか?
explicit/implicit learningについても理解すること。
Voice Qualityの節は省略,それ以降については各図が何を示しているか,
Activityはどのような問題かを説明すればOK。
<今日の目標>
<今日の出席確認>
- Activity 3 (a) keys の minimal pairs を録音し,学籍番号.wavを提出せよ。short-shortはshirtの誤り。
<notes for unit 14>
238ページに関して,以下はどのような教授法なのか説明してください。
- audio-linguarism
imitation, repetition,drilling, minimal pairs
- cognitive approach
language acquisition device (LAD), performance/competence
- communiacative approach
次に Activity 1 と Activities 4 を解説してください。教科書のそれ以外の部分は省略可。
<今日の目標>
<今日の課題>
- 昨年のQueen's speech の6:43から7:07までを書き取りなさい。
- 次のビデオから分かるこの言語の規則を書きなさい。
学籍番号.txtを提出。語彙は{cha, na, sha, zi}とする。
<notes for unit 15>
- tipsをデモしてください
- 日本人学習者の英語については,自分の日本語の発音をよく内省し,
教科書に書いてあることを疑ってみること。
<今日の目標>
<今日の課題>
- センター試験のアクセント問題7番について,それぞれ何音節の語か,何かルールはあるか,説明せよ。
- 前回練習した Jazz Chanz や
NHKのエイゴビートでリズムを学習することの長所と短所を述べよ。
- 日本語の[ɸ, ç, h]は,どのような環境に現れるか説明せよ。
- 学籍番号.txtをreportフォルダへ提出
発表用のpdfを,reportフォルダへ提出しておくこと。
Week 14 : Essay due / presentation
<先週の解答例>
-
○NHKのエイゴビートを用いたリズム学習において
長所:リズムに乗って英文法を学習できるので頭に残りやすい。流ちょうな発音の仕方を身につけることができる。
短所:リズムに流されて正しい英語の発音が曖昧になる。雰囲気で英語を読んでしまう。
-
長所
英語のリズムが簡単にわかる
楽しい、面白い
短所
会話における実用的なリズムではない
-
長所は、学習者の情意フィルターを下げ、英語にたいする抵抗心を和らげることができるのみならず、英語の音節感覚を自然に身に着けることができることである。
短所は、これらの方法は英語が自然に、そして流暢に話せるようになるためには有効であるが、読み書きなどテストの点や現行の授業のカリキュラムに直結する部分にはあまり関連がないため、後回しに、もしくは無視されがちであることである。
-
長所:英語らしいリズムの取り方がわかりやすい。
どこを強く読むのかということがわかりやすい。
短所:音に合わせようとするあまりに、リズムが早いところの単語を言わなくなるかもしれない。(小学校の英語の授業を見学した際、キーボードでベース音を流しながら会話練習をしていたが、多くの小学生がI want to be~がうまく言えず、Iを落としてwant to be~と言っていた。)
-
長所:リズムとともに英語を学習でき、記憶として定着しやすい。流暢な英語の発音の仕方を身につけられる。
短所:リズムにとらわれすぎて正しい英語の発音が疎かになる可能性がある。単語や文法への意識が低下する。
-
・リズム学習は耳に残りやすいため実際に発音するとき、そのままの発音をすることができるというメリットがある。特に小学生などの年齢の低い学習者は楽しんで発音できると思う。ただし、その楽しさが勝ってしまいリズムばかりに集中し、あまり言葉の意味が頭に入ってこないデメリットがあると思われる。
-
長所
・発話の強弱がわかり、強い部分を聞き取って、要旨をとらえることができる。
・真似をしやすい。
・NHKのエイゴビートは、リズムを体で覚えられて楽しいので、子どもが英語に親しみを持つことができるきっかけになる。
・あるリズムのまとまりで聞くことができ、ひとつの例文として身に付く。
そのひとつの例文を取り上げ、文法の勉強につなげることができる。
短所
・省略、弱く読まれがちな機能語に気づきにくく、それが無くても良いと思わせてしまうかもしれない。
・文法的な知識の習得を後回しにしかねない。
-
・長所
英語を話すとき、イントネーションやリズムを学習していると、相手に通じやすい。つまり、スピーキングに大変役に立つと考えた。それに伴いリスニングにも役立つ。日本の英語教育ではリズムに合わせて音読をしないため、抑揚がなかったり、リズムを意識したりしない。そのため、実際に外国人と話すとき、相手に伝わりにくい。
・短所
正しい発音やアクセントを学ぶ前に、リズムから学ぶと間違ったアクセントが身についてしまうと思う。
-
長所:リズムを覚えることによって単調に英語の文を発音するのではなく、音節ごとに区切って発音することによってネイティブに近いスピーキングをすることができるようになること。
短所:リズムを覚えることはできるが多くの文を学習するには時間がかかりすぎるため、少ない文でコツを掴み、ほかの文で応用することが難しい子にとっては学習したことがあまり意味をなさなくなってしまうこと。
-
ɸは ハ ヒ フ ヘ ホ の フ
両唇摩擦無声音
çは ハ ヒ フ ヘ ホ の ヒ
硬口蓋摩擦無声音
hは ハ ヒ フ ヘ ホ の ハ へ ホ
声門摩擦無声音
<今日の目標>
Week 15 : Defense / follow-up
<今日の目標>
(c) Katsumi NAGAI 2016 : Jump to
top,
Higher Education Centre , Kagawa University, 760-8521 JAPAN