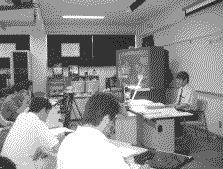本事業は、教員志望の教育学部生が、児童生徒と様々なふれあい活動をする中で、子どもたちの気持ちや行動を理解し、実践的指導力の基礎を身に付けることができるようにすることを目的に、学部授業科目「教育実践基礎演習」として実施されているものである。そして、フレンドシップ事業実施専門委員会を中心に、香川県教育委員会生涯学習課・香川県立五色台少年自然の家・香川県立屋島少年自然の家の協力を得るとともに、香川大学教育学部附属高松小学校・附属坂出小学校の宿泊体験学習と連携して企画実施されている。
平成15年度の参加者は29名であり、主な活動内容は、①オリエンテーション、②事前研修(関係機関の先生方を講師として)、③野外体験活動(A;屋島少年自然の家:附属坂出小の宿泊学習、B;五色台少年自然の家:指導者講習会(実技指導)、C;直島国際キャンプ場:附属高松小の宿泊学習)、④野外教育体験シンポジウム(まとめ)である。 本年度は、昨年度とほぼ同様な内容での取組みであったが、いくつかの点において改善を図った。例えば、オリエンテーションが説明だけで終始し、受講生の興味を引きつけるものとなっていないのではないかということから、前年度の受講生に、昨年度受講しての感想や、参加に際して
新しい学習指導要領のねらいを実現するためには、各学校における児童生徒や地域の実態等に応じた適切な教育課程の編成・実施や、指導方法の工夫等を行うことが重要であることは言うまでもありません。児童生徒の学習状況や教育課程の実施状況について適切な評価を行うことも極めて重要であると考えます。
平成12年12月に教育課程審議会から「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方」についての答申が出されました。各学校においては、平成13年度よりその答申の趣旨を受け、新しい観点での評価の具体化に向けての検討やその実施が行われてまいりましたが、その過程を振り返って、現在においても様々な問題や悩みを抱えておられるのではないでしょうか。そういった問題や悩みをとく手がかりになるようなものを求めて、今回の講演会を企画いたしました。
今回のご講演では、新指導要録において「目標に準拠した評価」が全面的に採用されたことによって、教育評価の研究と実践は新しいステージに立つことになったという問題意識のもと、教育評価の歴史や現状を押さえた上で、新しい教育評価の課題について、先生が監修された実践ビデオ等の視聴も交えながら、理論的かつ具体的で実践的なお話をお聞きすることができました。
100名を越える出席者があり、教育評価の問題についての関心の高さがうかがえました。また、出席者からは、「教育評価、歴史、意義、これからの方向等、よくわかりました」、「評価のあり方がとてもよくわかり、現場で明日から生かせる」、「2時間が大変短く感じました。大変有益な講演だったと思います」、「今、関心をもつ内容で大変参考になった。本も読ませてもらったが、評価の変遷もよく分かり、今の評価の求めていたことがよくわかった」等の感想が寄せられ、大変好評でした。
昨今、神戸、長崎をはじめ各地で起きている少年犯罪の低年齢化やそれに関わる心の問題、家庭、地域、学校等における心の教育の在り方が注目を集め、マスメディアでも大きく取り上げられていることから、「子どもたちの心の問題と心の教育~少年院・学校での心の問題や電話相談での声から心の教育を考える~」をテーマとして、パネルディスカッションの形で行われた。
これまでは、本学の教官が一人で講義形式で行われてきたが、今回は、法務省高松矯正管区教育課の山本善博課長様、香川県教育センター教育相談課の森山亮先生など学外の方の話題提供をもとに、「子どもたちの心の問題と心の教育」について、より広範な視点から考えることができた。
小・中・高等学校、養護学校関係者、法務局関係者、教育委員会関係者、香川大学教官、及び大学院生、学部生等30数名の受講者からの質問や意見も交え、熱のある議論が展開され、有意義な講座を開催することができた。
センター長の挨拶の後、まず、上記プロジェクトのメンバーであり、日本教育大学協会(以下、教大協)「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクト委員である長谷川順一教官(数学教育講座)による、教大協のモデル・コア・カリキュラム中間報告についての報告がなされました。その後、指定討論として、林俊夫教官(理科教育講座)、阪根健二教官(学校教育講座)からコメントをいただき、全体討議を行いました。
長谷川教官の報告からは、「教育実践を科学的研究的に省察すること」の重要性、「教育内容としての教員養成のコア 学部教官が協同的に担っていくためのコア」の必要性が 論点として浮かび上がりました。
論点として浮かび上がりました。
また、指定討論のお二人に先生方のコメントとフロアーの討議を通して、目標としての教師像、教師として最低限必要なもの、これまでの教員養成学部教育の評価、採用試験のあり方、公立学校における実習の位置づけ、学部と附属学校園との連携等、多岐にわたるしかしそれぞれ本質的な問題が改めて認識されました。
第2回センター研究会 テーマ「成功する少人数指導」と少人数指導の実践について
第2回研究会は下記の趣旨・日程で実施しました。
各附属学校園では、それぞれ特色ある実践研究を展開しています。それらの取り組みについては、研究発表大会で報告発表され、同時に研究物としても出版されております。しかし、各附属学校園が出版した研究物については、これまでは学部と附属学校園が共に検討していく機会はほとんどありませんでした。そこで、今回のセンター研究会では、香川県下の公立学校においても、現在手探りの状態で試行錯誤のもと実施されている、少人数指導に関する研究成果として、この度附属坂出小学校が出版した『成功する少人数指導』(明治図書2002)をとりあげて、研究協議を行うことを計画しました。
日 時 平成15年7月7日(月)16:00~
場 所 附属坂出小学校
提 案 森田浩文教官、森山敬三教官、東条直樹教官(附属坂出小学校)
指定討論 佐藤明宏教官(国語科教育講座)、植田和也教官(学校教育講座)
全体討論とまとめ
センター長挨拶のあと、附属坂出小学校の3人の先生方から提案していただきました。ここで、少人数の集団編成(興味関心型、相互作用重視型、習熟度重視型)の仕方、集団編成の留意点(コース選択のガイダンス、保護者への説明)、少人数指導の実際と問題(教員間のうち合わせ、教科による違いと課題)等が具体的に提案され、続いて、これらの問題を踏まえて、指定討論者のお2人の先生による提案への質疑とコメントがあり、全体討議をいたしました。
第3回センター研究会 テーマ「『学びの履歴』をつくる保育」
第2回に引き続いて、3回目は附属幼稚園の著作『『学びの履歴』をつくる保育~「人・ものやこと・自分」との関係づくりから教育課程へ~』(明治図書 2002)をとりあげ、下記の日程で実施しました。
日 時 平成15年12月15日(月)17:00~
場 所 教育実践総合センター3階・集団療法室
詳細は、次号のセンターニュースで報告いたします
平成15年度 第2回(11月期)教育実践集中講座
第1回(6月期)に引き続いて、教育実践総合センター客員教員による標記講座が実施されました。今回は、次のテーマと趣旨で、宮脇啓客員教授(塩江町立塩江中学校 教頭)と高木幸子客員助教授(香川県義務教育課 主任指導主事)による下記6回の講座が実施されました。
テーマ:“自分が好きみんなが好き”―ずっと心に残る道徳の授業&ぐっと心に響く生徒指導―
趣 旨:子どもたちが「生きる力」を身につけていくために必要な「心の教育」や、子どもたちの「問題行動への対応」、「生徒理解」などについて、道徳の授業VTRや具体的な場面を設定してのやりとりから考えていく。また、授業づくりについて演習を通して学
習する。
| 日 時 |
場所 |
内 容 |
10月29日(水)
(13:20~
16:20)
3時間
|
教授法演習室
|
講義・演習Ⅰ(宮脇・高木)
①心を耕し,心に残る道徳の授業実践
「命の大切さ」~君の命は君だけのものじゃない~
②授業づくり(かけがえのない命を感じる) |
11月10日(月)
(13:20~
16:20)
3時間 |
411教室
|
講義・演習Ⅱ(高木)
授業づくり(子どもの言葉で授業をつくる)
|
11月12日(水)
(13:00~
17:00)
4時間 |
教授法演習室
|
講義・演習Ⅲ(宮脇・高木)
①あなたなら,こんなときどうする?
―学校事故,人間関係,学習など―
②授業づくり(規範意識を育てる) |
11月19日(水)
(13:20~
16:20)
3時間 |
教授法演習室
|
講義・演習Ⅳ(宮脇)
心を耕し,心に残る道徳の授業実践
「愛」~愛は,充実した生き方から生まれてくる~ |
11月25日(火)
(13:20~
16:20)
3時間 |
411教室
|
講義・演習Ⅴ(宮脇・高木)
①あなたなら,こんなときどうする?
―いじめ,不登校,カウンセリングなど―
②授業づくり(紙芝居を用いて心に働きかける) |
11月29日(土)
【土曜日】
(13:00~
17:00)
4時間 |
教授法演習室及び集団治療室(実践総合センター3階)
|
講義・演習Ⅵ(宮脇・高木)
仲間づくり(ゲームを通してコミュニケーション)―レクリェーションあれこれ―
|
今回の講座も大変具体的かつ実践的で示唆に富んだものであり,参加した学生にとって有意義なものでした。
教育実践集中講座は、1月にも第3回を開講する予定です。詳細は「センターからのお知らせ」に掲載していますので、学生へのアナウンスをお願いします。
平成15年11月7日
研究主題
幼 児 期 の 学 び に つ い て 考 え る
~子どもと共に育つ保育者~
すばらしい秋晴れのもと、県内外から280名あまりの参会者をお迎えして研究発表会を行うことができました。大学の先生方、県・市の教育委員会の関係の方々には、大変お世話になりました。多くのご指導・ご助言をいただいたことを、心より感謝しております。
さて、今年度は、13年度に再編した教育課程に基づき実践を行いながら、幼児期の学びについて探っていきました。このとき、昨年度までの附属坂出学園での開発研究の成果を生かし、さらに、本園がこれまで継続してきた事例研究を続けていくことにより研究を進めてきました。
私たちは、これまで、子どもの側から「学び」を捉えていました。しかし、今年度は、保育者のサイドに立って、保育者の履歴を通して事例を読み解いていくことにより、子どもたちの学びを見つめていきました。経験の浅い保育者には新鮮で鋭い目があります。それを保育者集団で共有することにより、個々の保育者が保育の原点に戻り、もう一度自分自身を見つめ直すことができました。また、何年かの経験を経た保育者には、子どもの発達の見通しと実践を構想する力があります。それを、保育者集団で学び合うことにより、めざしていくべき保育者像を明らかにすることができました。
このようにして導き出したものは、保育者としての専門性を高めていくために大切な視点だと言えます。また、これらは、保育者が成長していく大まかな道筋であると考えました。つまり、私たちは、個々の保育者が資質向上を図っていくことのできる現場研修のあり方についても提案したいと考えたのです。
研究会当日は、公開保育の後、全体提案を行い、午後の分科会では、公開保育での具体的な子どもの姿や保育者の履歴を通して、幼児期の学びについて、話を深めることができました。
今後も、事例研究を積み重ね、それぞれが保育者としての専門性を高めていきたいと考えています。さらに、子どもたちの集団としての高まりと同時に、保育者集団としての質の向上についても研究の視点を当てていきたいと思います。

〈4歳児 帰る前のひととき〉
|

5歳児 分科会〉 |
第17回 日本教育大学協会・全国教育実習部門研究協議会 報告
平成15年10月10日(金)に大分大学教育福祉科学部を会場として標記の研究協議会が開催され、本センターから田上が参加し研究報告いたしました。協議会では下記の12本の研究報告について協議がなされました。
(1)教員養成カリキュラム開発の鍵概念としての実践的指導資質能力
-Performance-based Standardsを中心に- (兵庫教育大学 長澤憲保)
(2)実地教育・教育実習の実践的研究
-鳴門教育大学の場合- (鳴門教育大学 清水茂)
(3)地域から学ぶ教育実習
-へき地・複式教育実習の試行を通して (和歌山大学 川本治雄)
(4)中学校教育先行学生の主免教科選択の問題と課題
-教育実習事前指導の授業を中心として- (岡山大学 有吉英樹)
(5)教師の専門性を追求する教員養成カリキュラムの改善と教育実習
(琉球大学 小田切忠人)
(6)宇都宮大学における教育実習とそれに類似した教育実践活動について
(宇都宮大学 松居誠一郎)
(7)コアカリキュラムに向けた教育実習の在り方 (岡山大学 黒崎東洋郎)
(8)教育実習受け入れ公立小学校の児童および教師の意識 (香川大学 田上 哲)
(9)教員インターンシップで培われる資質・力量
-鳴門教育大学学校教育実践センターのもとに- (鳴門教育大学 梅澤実・芳賀正之)
(10)学校インターンシップ研修・教育実習の同一小学校実施の効果
-大阪教育大学第二部の試み- (大阪教育大学 奥埜良信)
(11)外国人の子どもの存在と教員養成
-インターンシップと教育実習の実験的実施- (群馬大学 所澤潤)
(12)大分大学教育福祉科学部における教育実習の現状と課題 (大分大学 神崎英紀)
なお、研究協議のあと、総合協議として『教育実習の管理・運営および指導に関する当面の課題』についての情報交換がありました。研究協議並びに情報交換を通して、各大学が、法人化を目の前にして、教育実習に関しても様々な取り組み・開発を行っているとの実感を受けました。また、『学校インターンシップの評価』(大阪教育大学 第二部 教育実践指導委員会)、『教育実習カリキュラムの改革~へき地・複式教育実習の試行~』(和歌山大学教育学部教育実習委員会)の報告書等が配布されました。これらの報告書をはじめ、本協議会の研究報告の資料につきましては、教育実践総合センターで所蔵しております。関心がおありの方は、ご閲覧ください。
香川大学が主催し、教育実践総合センターが担当した「香川大学免許法認定公開講座」が8月に終了しました。この公開講座は「教育職員免許法施行規則」第43条の3に基づくものであり、小学校、中学校、高等学校のうちいずれかの1種免許状を取得し、3年以上の教職経験を有するものに対して、専修免許状取得のための学修の機会を提供するために、本大学院で開講している授業科目を免許法認定公開講座として解説し、現職教員の資質の向上に寄与しようとするものです。
4年目となる本年度は、高知大学、鳥取大学、山口大学が共催となり、各大学の教員が授業を担当するとともに、各大学の会場を遠隔教育システムでつなぎ、遠隔授業を実施しました。本学部では、教育実践総合センターと併せて、同センター坂出分室も会場としました。
本年度の開設科目及び受講者数は下表の通りです。
開設科目名
|
講師名
|
受講者(人) |
香川 |
坂出 |
高知 |
鳥取 |
山口 |
計 |
教育情報特論
|
松下文夫(香川大)
村瀬康一郎(岐阜大)
山岸正明(鳥取大) |
44
|
26
|
12
|
23
|
6
|
111
|
教育臨床心理学特論
|
藤本光孝(香川大)
宮前義和(香川大)
名島潤慈(山口大)
井上忠典(高知大)
小林勝年(鳥取大) |
49
|
23
|
17
|
20
|
6
|
115
|
学校教育実践学特論
|
田上 哲(香川大)
加藤直樹(岐阜大)
林 徳治(山口大)
|
42
|
25
|
13
|
18
|
7
|
105
|
受講者からは、以下のような感想が寄せられました。
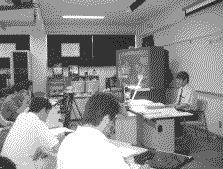
・遠隔討論は、講義の内容の理解を図るのにとてもよかった。その後に講師のコメントがあり、とてもわかりやすかった。
・これまでの疑問が解決できたと思う。まとめや位置づけができた。
・遠隔講義という方法は生かせないかもしれないが、教科に関する講義も取り上げてほしい。
・今抱えている課題について、違ったアプローチの方法を学ぶことができた。
学校教育総合研究センター年報第2号 上越教育大学学校教育総合研究センター
紀要 第23号 三重大学教育学部附属教育実践センター
生徒指導上の諸問題の現状と文部科学省の施策について 文部科学省初等中等教育局児童生徒課
教育実践研究 第12号 山形大学教育学部附属教育実践総合センター
心理教育相談室紀要 第1号 山形大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践研究第11号 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践ハンドブック-教科内容研究特集- 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
ファカルティ・ディベロップメント研究報告書 教員養成大学としての教育のあり方(4)第1分冊 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践センター「実践報告」No.26FDセミナー「セルフ・エスティームを高め学力向上を図る少人数授業づくり」 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践センター「実践報告」No.27第1部基調講演「評価・評定研究の最近の動き」第2部シンポジウム「評価・評定と学校教育」福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践センター「実践報告」No.28教育実践シンポジウム日本における教育の国際化-文化的共生の場としての学校- 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践センター「実践報告」No.29教育実践講演会 「ブリーフ・カウンセリングを教育に生かす」 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
平成14年度研究実習報告書 福岡教育大学教育実習運営委員会 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター
情報処理センターブルティン(北海道教育大学情報処理センター紀要)第8号 北海道教育大学
学校教育実践研究 第9巻 広島大学大学院教育研究科附属教育実践総合センター
平成14年度広島大学教育学部フレンドシップ事業ゆかいな土曜日実施報告書 広島大学教育学部フレンドシップ事業実行委員会
実技教育研究第17号 兵庫教育大学学校教育学部附属実技教育研究指導センター
教育実践研究紀要 第44号 福島大学教育学部附属教育実践総合センター
障害児教育実践センター年報第10号 岐阜大学教育学部附属障害児教育実践センター
教育実践センター紀要 No.9 静岡大学教育学部附属教育実践総合センター
学校臨床研究 第2巻第2号 学力低下の実態解明(その1)-関西調査から 東京大学大学院教育学研究科附属学校臨床総合教育研究センター
学校臨床研究 第2巻第3号 学力低下の実態解明(その2)-関東調査から 東京大学大学院教育学研究科附属学校臨床総合教育研究センター
横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合センター紀要第3号 横浜国立大学
教育実践研究紀要 第25号 秋田大学教育文化学部附属教育実践総合センター
第7回 秋田大学教育実践セミナー -子どもの学び 教師の学び 学校の学び- 秋田大学教育文化学部附属教育実践総合センター
教育実践総合センター紀要第26号 宇都宮大学教育学部附属教育実践総合センター
佐賀教育実践懇談会~佐賀の教育実践力の向上をめざして~ 佐賀大学文化教育学部附属教育実践総合センター
愛媛大学教育実践総合センター紀要第21号 愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター
教育実践総合センターレポート第23号 大分大学教育福祉科学部附属教育実践総合センター
学校臨床研究第2巻1号 学力低下の実態把握と改善方策-「学力問題プロジェクト」3年間のまとめ- 東京大学大学院教育学研究科附属学校臨床総合教育研究センター
教育工学・実践研究 第29号 金沢大学教育学部附属教育実践総合センター
IMETS No.149 No.150 財団法人 才能開発教育研究財団
コンピュータを教育に活かす 社団法人 日本教育工学振興会
生徒指導研究 第14号 兵庫教育大学生徒指導研究会2002年度
教育実践総合センター紀要No.13 2003 和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター
平成14年度教員養成学部フレンドシップ事業スクールボランティア活動報告書 和歌山大学教育学部 教育実践学教室・教育学教室
メディア教育研究 11-2003 メディア教育開発センター
札幌学院大学心理臨床センター紀要 第3号 札幌学院大学心理臨床センター
青少年相談機関の連携に関する調査報告書 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)
研究紀要 第16号
山口大学教育学部附属教育実践総合センター
生きる力を育む学習指導の充実-教育研究・実践の集積と展開- 大分大学附属教育実践総合センター
大分大学教育福祉科学部と地域との連携協力(報大分大学教育福祉科学部告書) 大分大学教育福祉科学部
学校教育学研究 第13巻~第15巻 兵庫教育大学学校教育研究センター
カリキュラム研究 第12号 日本カリキュラム学会
茨城大学教育実践研究 第22号 茨城大学教育学部附属教育実践総合センター
実技教育研究指導センター平成13,14年度 年次報告(第16号) 上越教育大学学校教育学部附属実技教育研究指導センター
教育実践研究 No.4 2003.9 信州大学教育学部附属教育実践総合センター
平成15年度松下視聴覚教育助成成果報告集 (財)松下視聴覚教育研究財団
平成15年度松下視聴覚教育助成成果報告集第9回研究開発助成報告集 (財)松下視聴覚教育研究財団
教育実践研究紀要 第13巻 鹿児島大学 教育学部附属教育実践総合センター




 論点として浮かび上がりました。
論点として浮かび上がりました。