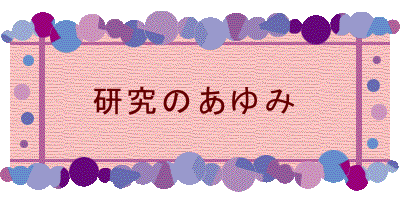
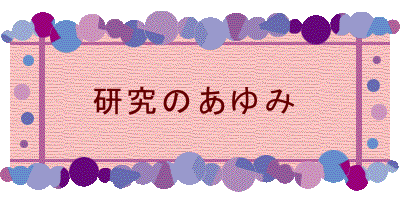
![]()
| 年度 | 研究主題 | 研究物 |
| 昭和39年 | 指導方法の改善 -練習の方法とその実践- |
・研究紀要5号 楽しい練習遊び |
| 昭和40年 | 幼稚園と小学校との関連にたつ -着想力を育てる指導- |
・研究紀要6号 幼稚園と小学校の関連にたつ 着想力の指導 |
| 昭和41年 | 課題遊びの実践 | ・研究紀要7号 課題遊びの実践 |
| 昭和42年 | 創造性をのばす課題遊びの発展 -主として自然を中心とする遊び- |
・研究紀要8号 自然を中心とする課題遊び |
| 昭和43年 | 積み木あそびの実践 | ・研究紀要9号 積み木あそびの実践 |
| 昭和44年 | 自主的に遊びにとりくめる子どもを育てる | ・研究紀要10号 自主的に遊びにとりくむ指導 |
| 昭和46年 | 試みることによって価値を創りだす指導 | ・研究紀要11号 試みることによって価値を 創りだす指導 |
| 昭和47年 | きまりをみつける遊びの展開 | ・きまりをみつける遊びの指導 |
| 昭和48年 | ことばの社会化をめざした遊びの展開 | ・ことばの社会化をめざした 遊びの展開 |
| 昭和49~50年 | いきいきとした遊びを育てるための指導法 | ・いきいきとした遊びを 育てるための指導法 |
| 昭和51年 | 幼児の心理に基づく指導法の開拓 | ・幼児の心理に基づく指導法の開拓 |
| 昭和52~53年 | 教育課程の編成とその指導法の改善 | ・教育課程の編成とその指導法の 改善 |
| 昭和54年 | 生活を高める教育課程の実践 | ・本園の教育課程 |
| 昭和55年 | 生活を育てる教育課程の実践 | ・生活を育てる教育課程の実践 |
| 昭和56年 | 自立感を育てる保育の構想と実践 -失敗経験の思索 その1- |
・自立感を育てる保育の構想と実践 |
| 昭和57年 | みつめ、みつけ、みなおす活動の組織 -失敗経験の思索 その2- |
・みつめ、みつけ、みなおす活動の組織 |
| 昭和58年 | みつける活動の組織 -失敗経験の思索 その3- |
・みつける活動の組織 |
| 昭和59年 | みつける活動の組織 その2 -思いやりの心を育てる- |
・みつける活動の組織 |
| 昭和60年~ 62年 |
子どもとつくる保育 | ・保護者の援助のあり方 ・互いに求め育ち合う友だち関係 |
| 昭和63~平成3年 | 子どもたちの幼稚園生活 | ・指導計画を考える1・2 ・一人一人の感じる心をみつめて ・一人一人の感じ考える心に応えて |
| 平成4~6年 | 幼稚園生活の充実をめざして | ・幼稚園生活の充実をめざして |
| 平成7~9年 | 保育者の専門性を探る | ・日々の悩みや喜びを語り合うことから ・子どもが育つ園生活をめざして |
| 平成10~12年 | 心を練る・自分探しへのいとなみ | ・関係づくりとしての幼児の 発達を考えるⅠ・Ⅱ・Ⅲ |
| 平成13年 | 幼児期の学びについて考える | ・幼少の学びの連続性を考えた 教育課程の再編 |
| 平成14年 | 生きる力を培う幼・小・中一貫した新教育課程の創造(附属坂出学園合同研究) | ・「学びの履歴」をつくる保育 |
| 平成15年 | 幼児期の学びについて考える | ・子どもと共に育つ保育者 |
| 平成16年 | 幼・小のなめらかな接続をめざした幼稚園教育の在り方を探る | ・研究開発報告書 |
| 平成17年 | 幼・小連携から見えてきた幼児教育 | ・5歳児の生活を見つめる |
| 平成18~20年 | 子どもの育ちを支える | ・人とのかかわりを見つめて ・伝え合う喜びを実感できる環境・援助を探る |
| 平成21~22年 | 協同への歩みを探る | ・「人・ものやこと・自分」との関係づくりから ・保育の構想と実践を考える |
| 平成23~26年 | 幼児教育の質を高める計画と実践の在り方を考える | ・主体性と協同性の視点から ・「教育課程・指導計画」 |
| 平成27~29年 | つながる -子どもたちの生活を支える- |
・体験の意味とつながり ・遊びの質の高まりを支えるアセスメントモデルの検討 |
| 平成30~令和2年 | 保育する -子どもとつくる明日- |
・今を生きること ・子どもの声を聴くこと |
| 令和3年~ | 保育を楽しむ保育者を目指して -自分(たち)らしさを生かした保育の展開-(R3-4) -資質・能力が育つ状況づくりを探る-(R5-6) |
・ティーム保育の充実 ・子どもとともに創る園生活 ・資質・能力が育つ過程とそのための状況づくり |
![]()